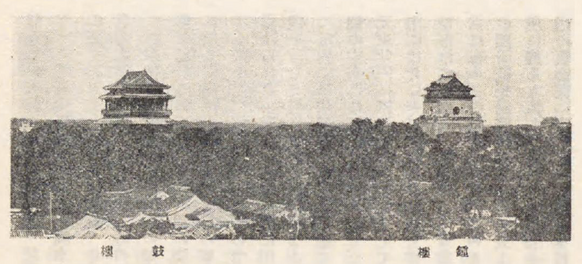昭和文学で旅する北京
鼓楼・鐘楼
鼓楼:
1272(元の至元9)年に創建された木造の時計台。当時は斉政楼という名前で、大都と呼ばれていたこの町のほぼ中心部に位置していた。大きな瓶から細い管を通って水が流れる仕掛けの水時計を使って時刻を計り、元から清の時代までずっと、大太鼓を打ち鳴らし角笛を吹いて人々に時を知らせていたという。
現在では、地安門外大街の北端に位置している。1420(明の永楽18)年と1800(清の嘉慶5)年に大規模な修復を受け、現在の建物は東西55.6m、南北34m、高さ31mの威容を誇る。もともと市街を監視する見張り台の役割も兼ねていたといわれる。内部は2002年の修復以降、一般公開され自由に上ることができるようになっているが、階段は急勾配になっているので注意が必要だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鐘楼:
鼓楼の北側100mほどの所に位置する明代に創建された時計台。1420(明の永楽18)年、時の皇帝である永楽帝が鼓楼と対になる形で造らせたのが始まりだが、一度火災で焼失しているため、現在の建物は1747(清の乾隆12)年の修築によるもの。鐘楼全体の高さは47.95m、楼内にはその名のとおり高さ4.5m、重さ63トンにもなる巨大な銅製の鐘が設置されており、1924年まで実際に使用されていた。その鐘の音は40km四方にまで響き渡ったという。
この大鐘の鋳造については、ひとつの伝説が残されている。永楽帝から鐘の鋳造を任せられた職人は腕利きであったが、それほどまでに巨大な鐘を造った経験がなかったために、どうしてもうまく鐘を鋳上げることができなかった。失敗続きの職人がとうとう永楽帝から死刑を命じられそうになると、それを見かねた彼の娘が何を思ってか銅が真っ赤に溶けたるつぼの中に身を躍らせた。職人は嘆き悲しんだが、娘の命を飲み込んだその銅を使って鐘を鋳たところ、ついに見事な大鐘を鋳上げることができたという。
(『地球の歩き方D03北京2016〜2017年版』ダイヤモンド社、2016年、152頁を参考。)